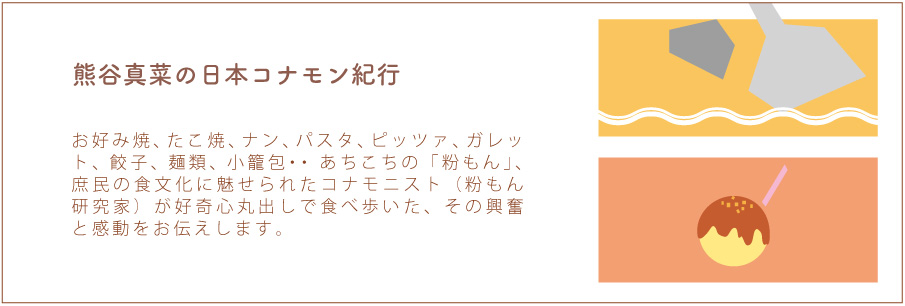
マレーシアの若者は、お給料がはいったらピザに行く、と言う。80歳近い母は、ナポリピッツァのおいしさに目覚めて、石窯を庭につくりたいと言いだす。以前、入院する祖母の付き添いで毎日、宅配ピザを注文していたらしい。祖母が一切れ食べたあとは、看護士さんの夜食になっていたと懐かしがる。
ピザor ピッツァ?
チーズとトマト、味覚の黄金コンビが、名脇役である生地に載せられ、老若男女、宗教問わず世界中で食されるようになってどのくらいたつのだろう。
日本では、ピザ、ピッツァ、両方ある。1975年、大阪万博で海外の食文化は一気に浸透するが、当時、ピッツァなんて言葉は知らなくて、アメリカ経由のピザ文化はチーズやトマトソースのおいしさ、要するに具材の魅力が必須だった。とにかく生地は後回し、ピザトーストも生まれ、クリスピーな煎餅風ピザ生地を本物?と錯覚していた時期もある。
アメリカンピザが流通すると、正真正銘の本物を知りたくなる。発祥のナポリにも関心は集まる。だが、イタリアン隆盛と本物ピッツァの普及は必ずしも一致しない。具材のバリエーションを楽しむピザではなく、生地が主役の石窯で焼いたナポリピッツァが日本でもこの10くらいで増えている。
その先駆けのお店、東京中目黒の聖林館におじゃました。鉄でできた外観、中に入っても、いい香りはするのだが、ピッツァらしいヴィジュアルは微塵もない。建物の脊髄ならぬ鉄の螺旋階段が地下から3階までつきぬけ、あばら骨のように巨大な石窯が正面に鎮座する。石窯といっても表は鉄で装飾され、芸術的廃墟みたいな色合いのなかに、薪の火が神々しい。まさに聖林館の心臓部ですね・・と思ったら、「この店は僕の好みだけで作りました。ピッツァはその一要素にすぎませんよ」と、オーナーの柿沼進さんはあっさりかわしてくれる。
聖林館のピッツァはマリナーラとマルゲリータの2アイテムのみ。トマト、モッツァレラ、バジリコの定番マルゲリータに対して、マリナーラは意外と知られていない。チーズを使わないタイプなので、日本ではメニューに入れる店も少ないが、18世紀中ごろに誕生したナポリピッツァの原形なのだ。イタリアのなかでも漁師さんの多いナポリ、手軽な食材をのせてさっと食べられる一食完結型のパンは重宝された。マリナーラの語源はマリンから。海の幸がのってなくてもマリナーラ、なのである。
その100年後、王妃マルゲリータがこよなく愛したマルゲリータは、マリナーラよりもちょっと贅沢ににんにく、オレガノの代わりにモッツァレラがはいった。ちょっとの違いだが、色合いも味わいも香りまでも、どっちを選んでいいか迷うくらいの王道2品が今でもナポリの定番だ。だが、2品しか出さないナポリの老舗に出かけたとき、ピッツァといえばチーズ、という固定観念があって、老舗の味を物足りなく感じてしまったのを思い出す。
ゆえに、柿沼マリナーラがどんな仕上がりなのか、気になる。
ピッツァの世界では有名人の柿沼さん。普通なら柿沼シェフ、といいたいところだが、彼にはそう呼ばせないオーラが漂う。人間柿沼の魅力を体現させたのが聖林館である、そこの主として、音楽、香り、味、語らい、オブジェ、空間、スタッフの動き・・すべてを指揮者のように奏でる立場であり、食材を操り、料理に専念しているだけのそこらのシェフとは格がちがう。
イタリア車好きな彼がつきあったイタリア人がナポリ出身だったこともあり、ナポリにしばらく滞在し、1995年、たまたま店を開こうと思ったときに、ピッツァのことを思い出し、日本にナポリピッツァの醍醐味を伝えることになった柿沼さん。名店サボイはもとより、2007年6月に建物ごとデザインした聖林館を堂々オープン。まさに知る人ぞ知る柿沼ワールドが実現した。
マリナーラとマルゲリータ、定番中の定番だけで勝負するところ、柿沼さんらしくて、惚れ惚れする。それだけに期待はふくらむ。ピッツァの生地に負けないよう、朝からふくらませて出かけた。
粉は熊本の地粉を使い、できるだけ少量のイースト、塩、水だけで生地を練る。できるだけじっくりねかし、大理石の下の引き出しには、ピッツァの生地が整列して待っている。赤ちゃんのお肌みたいな柔らかさ。小さな気泡がなめらかなすべすべお肌のなかに無数に見える。極限までの柔らかさ、取り上げると、そのままのびちゃいそうで、扱いに緊張が走る。ピッツァというと、天井に放り投げて延ばす曲芸も浮かぶが、このやわ生地を見たら、あれは邪道にしかみえない。
お好み焼のテコをつかって取り上げられた赤ちゃん生地は、両面打ち粉をつけたあと、大理石に置かれる。右のてのひらでおさえながら、左手でふちをつまんでひっぱり、なんとなくの丸に広がる。生地にできるだけ負担をかけないよう、柿沼さんの指が繊細に動く。ピッツァが円形である、という常識がくつがえされる。
トマトソースは、それほどたっぷりではなく、ふちをかなり残して広げる。丁寧に均一にソースを塗ると思い込んでただけにカルチャーショック。
そこにバジリコ1枚、にんにくを切りながら数枚、塩パラパラ、しめに香りたつオレガノを散らし、オリーブオイルをかけて、木のヘラ、パーラに移動させる。
まっかに熱い窯の右奥へ。すぐに、木屑を薪の上に入れて、温度をあげる。この窯、ナポリで見たどの窯よりも大きい。なぜなら、左で燃える薪とピッツァとの間隔が広すぎる。今度は鉄のヘラ、ピーラで、ピッツァを少しずつ回転させながら、窯の入り口にもってくる。薪の炎をあてて、ふちにわずかな焦げ目をつけるためだ。この焦げが、薪にしかできない香ばしさとなる。このひと手間のために、窯の広さは必要とみた。
生地はどんな感じがベストなんでしょう? とたずねると、「16歳の女性のお尻くらいかな・・」。真剣勝負
のあとの柿沼さんの笑顔に癒される。
引き出しから生地を出してから、窯の入り口に出てくるまで、2分かかっていない。あっという間の柿沼マジック。無駄がない、余計なことがない。生地がのびのびとふくらむためのちょっとした手助けのみ。あとは、この一枚のために必要最低限なことだけ。
なんといい香り。
一枚ごとに表情を変える、ナポリの芸術。
コルニチョーネ・・ピッツァの額縁といわれるふち部分が、オイルとソースとハーブが一体となった極上ソースを守ってくれている。
マリナーラがこんなにおいしいものだったのか。ニンニクの旨みがオイルに溶け出し、トマトとからみ、オレガノに出会って、私の口のなかに、今ここにいる。
ジュワッと広がるのは、あっさりとした深いコク。このおだし、何でできてんの?と言葉がでそうなほど、優しくて繊細なおだしになってる。不思議な感覚、初めての風味、これまでのピッツァが何だったのか、自分の舌に確認している。
そして、しめのふち。ほとんどソースはかかってなくて、生地の味が冴える。粉の旨みと食感を楽しむコルニチョーネ。もっちりというには、単純すぎる。
ふわふわというには、幼すぎる。ふわっとのあとの噛みごたえ。柔らかさと噛みごたえが交互にきて、止まらなくなる。ほんとは生地が主役。ソースやチーズこそ、名脇役だったのだ。ペロリとたいらげ、マルゲリータもお願いする。
逆らわず 生地の声をききながら おいしくふくらめ こなこな日和
番組用に柿沼さんからもらった「おいしくふくらめ」というフレーズ。
生地の力、自然のふくらみをじゃましないよう、柿沼さんはピッツァベイビーを見守っている。まさにピッツァの父、ピッツァマン。
450℃なんて家では再現できないので、どうしたら近づけるか質問してみたら、意外なことを教えてくださった。うまくいけば、いつかまたお知らせしますね。
(2011.08.03)